![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

反乱軍(向かって右)と会見するイングランド王リチャード2世(向かって左)。
彼は会見の席上、ロンドン市長ウィリアム・ウォルワースの裏切りに遭い非業の死を遂げた。
人影はキングスレイヤーに向かってオジギをした。
「ドーモ。キングスレイヤー=サン。リチャードです」
「ドーモ。リチャード=サン。キングスレイヤーです」
オジギ終了から0.02秒。
キングスレイヤーは跳んだ。
後悔は死んでからすればよい。
今は目の前の敵を倒さねばならない!
第一部・ネオロンドン炎上 「メナス・オブ・リチャードセカンド」より
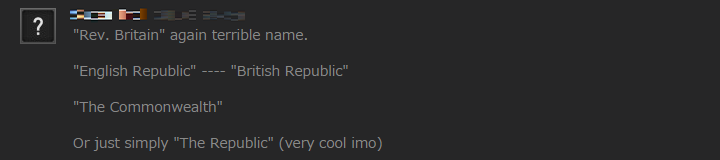
通例で England はイングランド、Great Britain はイギリスとしているけど、新規国家の Rev. Britain の日本語名どうしよう。
そもそも、Rev. Britain なんて名称はナンセンスだって、ワークショップの書き込みで本場イギリス人にダメ出しされているし。
じゃあ、なんで Rev. France はありなんだよと小一時間(ry
あと、English Republic か The Commonwealth の方が良いだなんて言われたけど、前者はまんまじゃん。何もひねりないし。
後者はポーランド=リトアニアの通称で既に使われているから分かりにくいんだよ~。
あげくに The Republic ( ̄∇ ̄)v ドヤッ! だもんなぁ~。
あ~も~やっぱ、感性って日本人と違うよねえ。
名作映画「スタンド・バイ・ミー」だって原題「死体(THE BODY)」だし。
・・・革命ブリテンでいっか。
↑は、AAR執筆中の回顧。
一時間後、「イングランド共和国」というぴったりなネーミングを wiki で発見しました。
Rev. Britain はイングランド共和国です!!

Arms of The Protectorate
Flag of Commonwealth
本MODで使用中の Rev.Britain の国旗(Flag)ですが、これは史実で、オリバー・クロムウェルが護国卿として事実上の独裁者となった1653年以降の国章(Arms/Emblem)です。
イングランド共和国(コモンウェルス成立時)の国旗とは異なります。
かっこいい方を選びました。
ちなみに、クロムウェルが独裁した共和制期を The Protectorate と呼ぶようですが、これまたゲーム中の「保護国(Protectorate)」と被ってて、ややこしい。
候補名として The Protectorate は一番最後まで残っていましたが、結局、Rev. France → 共和政フランス に準拠させました。
以上、Rev. Britain の言い訳でした。

5th Lord Protector Humphrey Lancaster
グロスター公ハンフリーは 2/2/3 のイマイチぱっとしない護国卿(第5代)である。
彼の生家ランカスター家は断絶したプランタジネット王家の分枝で代々護国卿を務める国内屈指の大貴族である。
1st Lord Protector John Plantagnet
グロスター公ハンフリーの祖父にあたる。
ジョン・オブ・ゴーント(John of Gaunt)とも呼ばれる。
彼はワット・タイラーの乱を鎮圧し、指導者ワット・タイラー、ジョン・ボール、そして「王殺し」のロンドン市長ウィリアム・ウォルワースらを捕縛、処刑した。
非業の死を遂げたリチャード2世の“仇討ち”を果たした功績は大きく、次期国王の最有力候補者とみられたが、その偉大な功績が却って仇となり、他の王位継承者からの反発と妨害、議会の警戒を買ってしまい、結局、国王にはなれなかった。
共和体制をめざす議会との妥協を経て国家首班の“護国卿(Lord Protector)”に就任する。
図らずもこれが、後に続く護国卿体制(The Protectorate)の嚆矢となった。
2rd Lord Protector Henry Lancaster
グロスター公ハンフリーの父にあたる。
ヘンリー・ボリングブロク(Henry Bolingbroke)とも呼ばれる。
アイルランド征服を敢行したことで有名である。
彼もまた、その功績をもって王位を請求するも、ヨーク家、ボーフォート家など、前王家に繋がる有力貴族らの反対、妨害にあい挫折する。
3rd Lord Protector Henry Lancaster
グロスター公ハンフリーの長兄にあたる。
祖父ジョン・オブ・ゴーント、父ヘンリー・ボリングブロクの悲願たる王の地位を渇望した。
彼はフランス共和国の内乱に乗じ、両国の戦争を再開、同国を併合するという“偉大な功績”をもって王になろうとしたが、パリ近郊の戦いの最中に急逝する。
4th Lord Protector John Lancaster
グロスター公ハンフリーの次兄にあたる。
ベッドフォード公に叙された。
彼は急逝した兄ヘンリーの跡を襲い護国卿(戦時代理、後に正式に認められる)に就任する。
フランス国内を転戦し、兄急死後の劣勢を挽回するも自身もまた急逝する。
1444年のヨーロッパ
フランス、スペイン、オーストリア、ロシアなど地域大国が勃興している。
勢力均衡(Balance of Power)がはかられ突出した大国は存在しない。
イングランド共和国は大陸領こそ失うもグレートブリテン島全域を掌握している。
1444年のアメリカ大陸
13世紀の終わり頃から大航海時代が始まり、新大陸には各国の植民地が成立する。
15世紀に入ると各国の植民地統治も円熟の域に達し、より高度な自治が行われるようになる。
イングランド共和国はアメリカ領主連合(USA)、カナダ(Canada)、ニューファンドランド(Newfoundland)などの自治領(Dominion)を有する。


護国卿ハンフリーは自らの才能が非凡な兄達と比べるまでもないことを十分に自覚していた。
彼は凡庸である。
しかし、自分をそう自覚していたからこそ、身を厳しく律し慎重な国政の舵取りを心がけた。
彼は百年戦争敗北の痛手から国力を回復することに努めた。
まずは軍縮である。
陸軍・海軍の維持費は最低まで引き下げられ、軍備で圧迫されていた国庫収入の是正がはかられた。
グレートブリテン島全土を掌握する共和国にとって、脅威とは海を隔てた大陸諸国である。
この軍縮は当面、本土への侵攻が無いと判断した上でのものであった。
次に、軍縮によって生じた潤沢な予算を投入し、優秀な閣僚を雇用。
彼らの打ち出した諸政策(Decision)を次々と実行していった。
特に内政面の充実に焦点を定め(Administrative への National focus)、大蔵卿による経済政策(Economic アイディアの取得)を推し進めた。
West African Chapter
シエラレオネ(Sierra Leone)を本拠とするアフリカ貿易会社の支所で“奴隷貿易”の中心地でもある。
South African Chapter
ケープ(Cape)を本拠とするアフリカ貿易会社の支所。
また同地はボルドー、ギュイエンヌ地方の葡萄栽培者が入植したため、ワインの産地でもある。
西アフリカのシエラレオネ、南アフリカのケープの居留地は、喜望峰周りの欧印航路の開発により、欧州と東洋を結ぶ主要航路の補給基地である。
通商卿アルフレッド・ハーバート(Alfred Hertbert)の建議により、これらの居留地はアフリカ貿易会社の管轄下に置かれることとなった。
アフリカ貿易会社は“香辛料貿易”の独占権を与えられた特許会社であり、共和国が進める重商主義体制の象徴でもあった。
争いの火種は何時の時代も尽きぬものである。
共和国は宿敵フランス、スペイン、カルマル同盟と西インド諸島植民地の帰属をめぐり、深刻な対立状態にある。
このたびのサルデーニャ=ピエモンテ、ハノーファー、プロイセン、ポルトガルとの同盟締結は、領土問題を抱える敵対国への牽制を企図したものである。
ジャマイカ島(Jamaica)とバルバドス島(Barbados)を自国領土に編入(コアプロヴィンス化)し、委任統治領“英領西インド(English Wset Indies)”を成立させる。
尚、同委任統治領はバハマ島(Bahamas)、タークス・カイコス諸島(Turks Islands)など、スペインが領有権を主張する島々が含まれている。
現地駐留部隊が設立されるまでの間、共和国海軍(Commonwealth Navy)を派遣し、スペインの襲撃に備えることとした。
1447年、プロイセンはオーストリア領ハンガリーのスピス(Zips、カタカナ表記はハンガリー語に倣う)の征服を企図。
オーストリアに宣戦布告した。
プロイセン陣営には、スペイン、サルデーニャ=ピエモンテ、オーストリア陣営にはカルマル同盟はじめ、ヘッセ、プファルツ(ライン宮中伯)、ヴュルテンブルク、ヴュルツブルクが参戦。
大陸全土を巻き込む大戦となった。

New Model Army
初代護国卿ジョンが創設した新編制の軍隊。
共和国も英普同盟に基づき参戦を表明。
護国卿ハンフリー直卒の新模範軍(New Model Army)3万5,000名は、共和国海軍(Commonwealth Navy)の援護の下、同盟国ハノーファー領イーストフリーシア(Ostfriesland)に上陸。
同地で補給を受けた後、オーストリア領ボヘミアを目指しエルベ川沿いに進軍する。
新模範軍はオストマルク(Ostmark)でオーストリア軍と交戦、撃破するも補給が続かず、プロイセン領ブレスラウ(Breslau)に撤退。
以降はプロイセン軍と共闘し、チェコ方面でオーストリア軍を迎撃する。
どうやらプロイセンの主力はスピスの目前、モラヴィア(Mähren)でオーストリア軍に奇襲され総崩れとなり、以降は苦しい防戦に追われているようである。
新模範軍の到着により、プロイセン軍はチェコ戦線を維持することに成功。
突出するオーストリアの分遣隊を5度ほど撃破すると攻勢は弱まり、プロイセン軍単独で戦線を維持することが可能となった。
新模範軍は前ポンメルン(Vorpommern)に上陸したカルマル同盟軍の迎撃に向かう。
難なくカルマル同盟軍を追い払った新模範軍であったが、消耗が激しく一旦、本土に戻ることに。
その間、チロル方面ではサルデーニャ=ピエモンテ軍がオーストリア軍と対峙。
一進一退の攻防が続くが、山間の隘路に陣を構えたオーストリア軍が堅く守りに徹したため膠着状態に。
また、スペイン軍はオスマントルコ軍とギリシャで対峙中で、援軍を出せる余裕もなく、戦況はオーストリア優位に進む。
1451年4月2日、プロイセンがオーストリアと講和。
講和の条件はプロイセンがアンスバッハ(Ansbach)とチュートン騎士団(Teutonic Order)の宗主権を手放し、オーストリアへ賠償金84ダカットを支払うというもので、プロイセンの実質的敗北である。
共和国は得るものもなくただ徒に兵士を失い、大陸派兵は失敗に終わった。